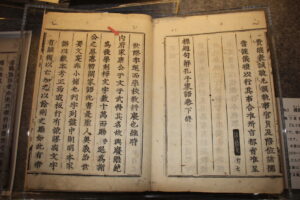7月20日(日)足利市民プラザ(あしかがフラワーパークプラザ)で足利映像クラブ主催『松島健一朗 個人映写会』が開催された。多くの映像ファンが会場を訪れ、松島さん(85)の60年に渡る映像作品を楽しんだ。また、松島さんより来場者全員に、当日上映された作品のDVDが進呈された。
幼い頃から映画好きだった松島さんは、日本映画の黄金期と重なる青春時代を過ごし、25歳のときに8ミリカメラを手にしたことがきっかけで、一度は映画製作の世界で生きようと決意。しかし家業(足利市内の時計店)を継ぐことになり、趣味で映画製作を始める方向に舵を切った。現在は、2010年に足利市生涯学習センターの映像編集講座終了後に結成された「足利映像クラブ」(石川勝 代表)に所属している。
今回の個人映写会では、家族の記録、職人の匠の技、自然の美しさ、人の暮らしを追うドキュメンタリーなど、各10~20分の短編を10作品上映。どれも撮影者の情熱と愛情が画面から伝わり、会場全体が松島ワールドに引き込まれていた。
冒頭の1971~72年に撮影した『家族誕生』は、29歳で家庭を持ち、親となった松島さんが8ミリカメラを向けた、ホームムービーの原点と言える作品。その後も、年子で生まれた兄妹の日々の成長を追う『なかよし』など、子どもたちの瞬間、瞬間の愛らしい仕草や、ハラハラ、ドキドキしながら見守る作者の視線が、観ている観客の視線と重なって、我が事のように思えてくる。
しかし、現代の撮影機材と違い、8ミリカメラを使っていたこの時代、暗い室内でタイミングを逃さず撮影することはかなり難しいことのように思える。「自宅の天井のあちこちに撮影用の照明を仕込み、スイッチ一つでライトが点灯するようにしていました。」と松島さん。自宅はほぼスタジオ化していたようだ。
また、『土の詩』『飛騨の匠』『奥能登、とり残されし者』などは、緻密に取材を重ねたドキュメンタリー映像。1979年の『土の詩』は、オカリナ奏者(製作)の故火山久氏の工房を密着撮影している。このとき工房にいた3人の弟子の1人が、のちにオカリナの第一人者と言われる宗次郎氏だった。現在は解体されてしまった、足利市民会館で開催された「オカリナコンサート」で演奏する、火山氏等4人の姿も収められている。
2019年の『古都の春 花と龍』は、桜の花が大好きだった奥様との最後の京都旅行記になっている。満開の桜の見事な美しさや、建仁寺「双龍図」の迫力ある天井画などを追いつつ、ご夫婦の大事な思い出が綴られている。
上映後、ゲストとしてJAVCA 日本アマチュア映像作家連盟の重鎮である金子喜代子氏が登壇し、「映像づくりはフォームビデオが基本、その基本に忠実な作品です。人生において作品を残すことは、自分自身の励みになります。松島さんの生きた証し、世界に一つの作品を見せていただき感謝します。」と同映写会向け賛辞を贈った。金子氏は「東京ビデオフェスティバル2020」にて「こころみ学園」と「ココ・ファーム・ワイナリー」を描いた作品『聖者のぶどうと奇蹟の滴』で、<TVFジャーナリズム賞>を受賞している。
映写会の終わり松島さんは「25歳のことから、どこに行くにもカメラを手放しませんでした。これからも作品をつくり続けていきたいです。私のことは、作品の中で語り尽くしました。今日は我が人生で最良の日です。」と喜びの言葉で結んだ。