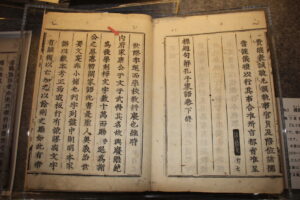足利大学工学部渡邉美樹教授より、『大野水車』の部材を大学で引き取り、将来的に可能な限り組み立てる計画があるとの情報をいただいた。大野水車(足利市大前町)は、明治18年水車による営業を開始し、昭和43年頃にはモーターが動力として使用されるようになり、その役割を終えることとなった。
この度、この水車が解体され保管・利用されている、木造家屋が取り壊しになるため、足利大学で水車の部材を引き取るという。大野水車の当主大野常雄さんに、当時の建屋がその姿を残している間にと取材をお願いし、弟の寺内美知夫さんと共に、大野水車について話を聞いた。




大野家9代目の当主である常雄さんは『大野水車』の屋号で昨年まで米屋を営んでいた。
「現在の地に移り住んだのが、両毛地域の和算家と言われた5代目源七郎でした。明治末期にかけ、この辺りの柳原用水の分水には、小型も含め8軒の水車がありました。大野水車は柳原用水から自家用の堀を設け、水を引き込み、家屋の下を通し、家屋の中央に据えた水車を動かしていました。その直径は6m、幅1.8mの木造で出力は15馬力。この水車で米つき、押し麦づくり、粉ひきをしており、米つき用きね12本、ひきわり1台、製粉機3台が設置されていました。明治の末頃からは、これに3台の八丁撚糸機が加わり、撚糸業も兼ねていました。これら全て1台の水車で同時運転していたのです。その上、隣の2軒に撚糸用動力を分けて2軒で合計9台の八丁撚糸機も回していました。」当時の地域の動力源として、なくてはならない水車だったと常雄さんは振り返る。
昭和40年代モーターにその役割を譲るまで活躍した水車は、解体され堀は埋められた。水車に愛着を持つ当時の当主であり常雄さんの父源一郎さんの提案で、水車材は母屋の部屋を改造したおり、床・天井板としてまた壁に埋め込まれるなどの形で利用された。その母屋がこの度、解体が決まった木造家屋である。
長年に渡り地域の生活を支えてきた『大野水車』が、足利大学工学部の教授・学生の手によって、蘇る日がくることを心待ちにしていたい。



写真 浦島大介