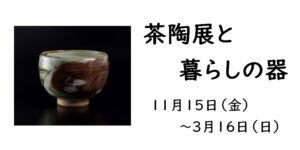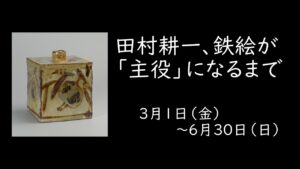茶陶展と暮らしの器
やきものに興味を持つようになったのは学生時代。東京美術学校(現東京藝術大学)に入学し、人形師である父(林次)の意向により学部は工芸科図案部を選択。食器として絵具皿に兼用できる白い西洋皿を使っていた。食風景に凝る性分だったらしく、暮らしで使う器に物足りなさを感じて、古道具屋へ出入りするようになったという。そこで伊万里焼や朝鮮李朝の陶磁器に出会い、陶磁器との幸せな関係が始まった。二十一歳の時、益子の濱田庄司(当時四十五歳)を訪ね、飯茶碗を買い求めようとしたところ、「学生からお金はとれない」と言われ、蓋つきの茶碗四個を無料で譲ってもらったこともあった。使いこむことで表情を変えていくその「茶盌」は、日々の暮らしを豊かにしてくれたことだろう。
「もっとも原始的な作業のなかから、玉にまさる美しい、にごりのない
私たちが日常的に使うものができるとしたらどれほど幸せなことでしょう。
科学的にまだ解明されてない多くの部分をのこしながらも 火によって焼きかためられ
ながい年月をつくり続けられた陶磁器を
特に私たちの日本の風土のなかで生かしつづけ
手でつくりうるものとして、のこしたいものです。
私たちの生活のなかにあって
つくるたのしさを知ってほしい
観るたのしさを知ってほしい
そして、使うたのしさを知ってほしい。」
引用:陶芸入門.田村耕一著.一九七七年
本展では田村の茶陶の世界と日々の暮らしの器を紹介したい。土と釉薬を使い、やきものでしか表現できない「文様」と「形」の融和を。
立体な器のフォルムに、計算された絵付け、それは多彩な釉薬の組み合わせと数々の技法によって生み出されている。好んで描いた文様は、自宅アトリエの庭や、カメラ片手に散策した渡良瀬遊水池の、ほたる袋、竹、梅、柿、柘榴、ススキ、葡萄から蝶や鳥などの動植物。どれもごくありふれたものばかりだ。その目に生きものの本質を捉え、抽象化して映し出したその絵付けは洗練されていて、素朴さと品位を纏っている。茶盌ひとつにおいても、先人によって既に尽くされた茶盌づくりの限界に挑み、創意に満ちた絵付け、釉調、確実な焼成と、それを楽しんでいるかのようでもある。今日の私が心惹かれるのは青磁茶盌だ。代表技法の「鉄絵」も文様も用いないその佇まいは見栄えせずとも、何か心をくすぐる色調があり、文様のあるものと比べても遜色なく別格な貫禄がある。
会期
〜3月16日(日)
料金
無料
問合せ
TEL 0283(22)0311
人間国宝田村耕一陶芸館
当館では、佐野出身の陶芸家で東京芸術大学教授を務め、昭和61年に人間国宝の認定を受けた田村耕一の作品を展示しています。
田村耕一の世界「鉄絵陶芸の美」をお楽しみください。
〒327-0022
栃木県佐野市高砂町2794-1
0283-22-0311
https://www.city.sano.lg.jp/sp/tamurakoichitogeikan/index.html
開館時間
午前9時~午後5時
休館日
12月30日~1月1日
(臨時休館日あり)
駐車場
佐野市庁舎駐車場
市営駐車場あり
大型バス可(要予約)